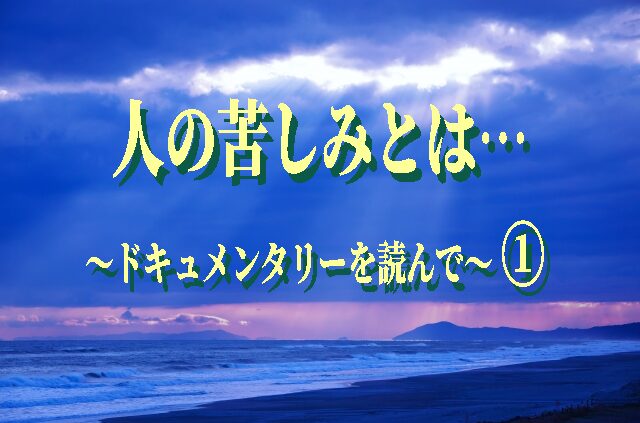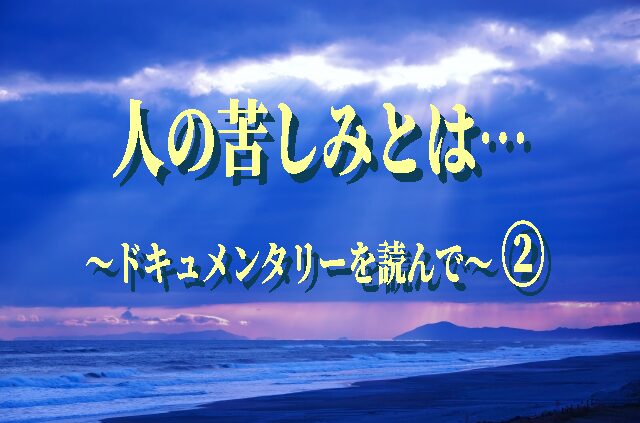今年の私は、ドキュメンタリー本ブームでした。
「ノンフィクション大賞」をとった本を何冊も読みました。
どの本も、長期に渡る綿密な取材を通した深い考察によって
人間の本質・社会の本質にせまる、得難い読書体験でした。
テレビのニュースやドキュメンタリー・ネットでの情報では
決して得られないものが、本の中にはたくさんありました。
中でも特に心を揺さぶられた本をご紹介します。
■『ソ連兵に差し出された娘たち』著:平井 美帆
日本の敗戦後「満州国」に取り残された黒川開拓団で何があったのか?
まず、この本が出版されたが 2022年と最近のことで
取材対象者の年齢は80代90代だったのに、これだけ多くの取材が
出来ていることに驚きました。
著者の親身な取材もあったかと思いますが、当時のこと帰国後のこと
大変な目にあったことが、長い年月を経てもなお鮮明に記憶に残っている
という事の重さに心が痛みます。
厚い本ですが、2日で一気読みしてしまいました。
本の半分が帰国後の話で、日本に帰っても差別され侮辱された事が
現代にも通じる性被害の苦しみの深さを思わずにいられません。
この本の真骨頂は、時間をかけて丁寧に取材した中でしか聞けない話
の数々だと思います。
私が泣いてしまったのは、下記のシーンでした。【以下ネタバレ】
“初恋の彼女が満州で中国人へ性接待させられたことを後で知って
彼女をいっぺんで嫌いになってしまった” という話を
著者は弟さんへの取材で聞いて、亡くなった姉の善子さんが生前
「谷に千丈の谷に落ちる感がした」と語っていたのは
この事だったのかと気づきます。
著者は弟さんに「彼女は何も悪くないんですよ。それを聞いたお姉さんの
気持ちを考えなかったんですか」
「お姉さんは、彼女と同じ様にソ連兵の接待に行かされてたんですよ」
と詰め寄ります。
著者が何度聞いても、弟さんは
「(俺だって)ショックだよ、(女は)操(みさお)が…」
「男はねぇ、新しいのが欲しいの。独占欲が強いの」
と自分の気持ちしか言えません。
協力してくれている弟さんに対して取材者としてどうかと思いましたが
長く取材した姉の善子さんのことを思うと、言わずにはいられなかったのだと思いました。
私はここを読んで
” もう80歳を超えた古い考えの男性に、何を言っても響かないだろうに…
今さら彼を責めることに何の意味があるのか…”
と思っていました。
ですが、やがて弟さんから
「姉さんがそんなこと傷つくの、今日初めて知った…。
姉さんが俺にそういう気持ちを知らせたくて、あんたを寄こしたのかも知れん。
姉さんがあんたを連れてきた」
というの言葉が出たのです。
この展開はあまりに予想外で、
” お姉さんの思いが届いたのだ!
自分の苦しみを、弟には知って欲しかったという気持ちが…”
と、私は涙が止まりませんでした。
…読んだ翌月に、私は母と夫と車で片道5時間かけて「満蒙開拓平和記念館」と
旧黒川村の佐久良太神社にある「乙女の碑」を見に行きました。
長いトンネルの先に、旧黒川村がありました。
トンネルを出てすぐの所に神社があるのですが
車のナビは なぜか神社から3km先の村の端の地点を差していて
私達は図らずも村全体の印象を知ることが出来ました。
そして感じたのは、この小さな村は
山に囲まれて昔は陸の孤島に近かったであろうことです。
その村は生活圏の全てであり、生活と仕事を共にする隣人であり親戚であり
濃密な関係性があったはずです。
それが、「国策(村による推進)で、満州に行った人・残った人」という分断
「満州から帰れなかった人・帰った人・村で迎えた人」の間にある分断
「性被害にあった女性・その女性を差別し侮辱する人」との分断による
加害者と被害者のような構図があり憎悪・嫉妬・差別が
その小さな村の中に、何十年もあったのだろうと感じました。
「乙女の碑」は長い間その名前以外の説明が全く無かった(史実を表に出さず
被害少女の供養目的)のですが、2018年になって説明パネルが設置されました。
その内容は驚く程に詳細で、被害女性へ謝罪し平和のための教訓として
語り継ぐことを綴っていながら、同時に
黒歴史に翻弄される村の方々の苦しみも感じました。
この史実を表に出すことを望まない人は、遺族会にも被害女性にもいたでしょう。
記念館では、多くの資料をそろえて関係する本の販売も行っているのに
この本を置いていません。それが、残念でした。
事情は、「満蒙開拓平和記念館」のHPに下記の記載が出ています。
『旧黒川開拓団をとりあげた書籍に対する遺族会の声明文と記念館のコメント』
国策への批判になるせいか、この記念館はなんと「民営」です。
原爆死者数は広島14万人・長崎7万人に対して、この満蒙開拓による死者数は
8万人です。学校の教育やニュースで、もっと取り上げていいはずです。
他国への加害どころか、自国民への加害に対しても多くを認めようとしない
日本とという国を感じずにはいられません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
映画 『黒川の女たち』を見ました。とても良かったです。
本とは違った角度の取材と関係者の生の声・表情を知ることが出来ました。
戦後80年を迎え、日本はやっと『性被害』を表に出せるようになりました。
今まで、社会組織は意図的に黙殺していたことは映画の中にも出てきます。
心に残ったのは、99才の被害女性の言葉です。
「日本が、戦争に負けて良かった」
もし勝っていたら、彼女の満州での苦しみも、それ以上の帰国してからの
差別や侮辱による長い苦しみも無かったにもかかわらず、その言葉が出たこと。
「戦争反対」は誰でも簡単に言えます。
しかし、「負けて良かった」は、歴史的にその通りであるにしても
誰もが言える言葉ではありません。
その意味を、私たちは深く受け止めなくてはいけないと思いました。
読書は子供の頃から好きでしたが
私は今回はじめて賞をとったドキュメンタリー本を読みました。
こんな読書体験があると初めて知りました。
テレビや雑誌のドキュメンタリーは、そこにある問題を可視化して
これからその問題とどう向き合うかを問いかけてきます。
本の場合は、問題の可視化のさらに深い所、そのテーマを軸にして見ると
人間とは社会とはどんな姿なのかを見せつけてきます。
そして、読者それぞれの中にある
「”自分の” 困難や苦しみとの向き合い方」
について問いかけてきます。
ノンフィクションだからこそ強烈に迫ってくる現実がそこにあって
「この現実の中で、自分はどう生きるのか。
生きることが出来るのか」と。